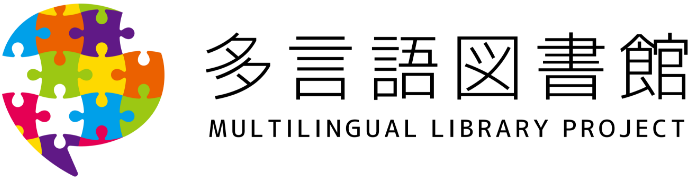赤い羽根「外国にルーツがある人々への支援活動応援助成第4回」によって行った事業の報告
◆本助成で行った事業(活動)の概要
本事業では①地域のニーズ調査、②広報活動、③多言語本棚の設置、④国内外の協力者の確保、⑤蔵書の収集および寄贈の受付、⑥拠点間の交流活動、⑦ウェブサイトの翻訳を行いました。
①では下関市、宇部市の市役所に外国人についての情報提供を求め、協力を得ました。また各拠点とも協力して、地域の外国人に関する情報を集めました。また外部の専門家の協力を得て、北九州市、下関市、宇部市のネパール人の調査を行いました。
②各拠点と協力して、地域の行事に参加し、広報活動につとめました。また図書館関係の研究者に取材を受けたほか、山口県の開催する「県民活動新規事業コンテスト」にエントリーし、上位6団体に選出され、広報活動の機会を作ることができました。
③北九州市、下関市、宇部市、福岡市に多言語本棚を設置しました。
④ニーズ調査と広報活動を通じて、国内外の協力者の確保に努めました。
⑤では世界各地の協力者との連携によって、本を選定・購入し、寄贈を受け付けました。
⑥では拠点の運営者同士の交流と情報交換の機会を増やしました。またベトナム出身者やベトナム語に習熟した地域の人たちの協力も得て、ベトナム語学習会を実施しました。
⑦ではあらたに10言語の翻訳をおこないました。
◆本助成による事業の成果
①下関市、宇部市より情報提供を受けました。また田中雅子氏の協力の元、地域のネパール人についての調査を行いました。多言語本棚を設置している各拠点で情報交換を密にし、外国にルーツのある人や外国語に通じた人たちに適宜対応することができました。
②「マイクロ・ライブラリーサミット」を始めとする各種イベントへの参加、日本語教室、北九州国際交流協会、北九州ベトナム人協会への訪問、雑誌、新聞への取材対応のほか、外国にルーツのある人たちが使用するSNS上での告知もおこないました。各拠点が積極的かつ自発的に情報発信をしてくれたことで、より広く情報を拡散できました。
③ネパール人たちが集う、宇部市、北九州市のヒマラヤおよびアサに本を設置できました。この調査の過程で50人のネパール人から話を聞きました。中心的役割を果たしてくれたのは、幼少期に来日したネパールにルーツをもつ下関市の青年です。留学生がアルバイトをしている純珈琲では、大学に近い立地から「日本人の関心を促し、留学生をはげます選書を」とのリクエストがありました。宇部市の仲介によって実現したボスティビルドへの設置は、1階で働くベトナム人と、日本語学習を希望する人たちが訪問しやすく、ベトナム語の本を中心に選書し、日本語学習に役立つ本を設置しています。宇部市のピッコロコーヒーでは、本を借りやすいよう店外に設置してくれました。福岡市にある居場所カフェ「在」は、ここに通う外国人のための選書をおこないました。
④広報のために訪問した場所で帰国する人たちに協力をお願いしたり、昨年同様、エスぺラント語のネットワークを活用したり、認定NPO法人Ivyの近藤理恵氏や上智大学の田中雅子氏ならびに博士課程の織田悠雅氏の協力を得ました。
⑤日本各地からモンゴル語、ベトナム語、インドネシア語、英語、中国語、ネパール語、フランス語、日本語の計94冊の寄贈をいただきました。また本助成で、ベトナム語、インドネシア語、スワヒリ語、英語、タガログ語、クメール語(カンボジア語)、日本語の本を購入いたしました。
⑥ベトナム語学習会(25人)でベトナム語の挨拶を習得した方が、職場で10人のベトナム人とベトナム語で会話することで親しくなり、そのベトナム人たちが友人らに話を広めたことで、ベトナム語の本の利用につながりました。
⑦ではサイトの対応言語を13言語まで増やしました。(更新作業中)
◆事業を実施する中で見えてきた課題と今後の取り組み
外国人集住地域でなく、人的リソースにも限りのある地方都市に、国内外の人たちとの協同によって、外国にルーツのある人たちの図書館を作るという試みは、2年間の活動で前年の3倍の協力者を得て、軌道に乗り始めたように見えます。また分散型多言語図書館という形態は各拠点の特徴と発意を発揮できる点においても有効であることが確認できました。
他方で、下関市のような車社会では、多くの外国人が拠点を訪れることさえ容易ではないことが明らかとなりました。この課題を解決するため、地域の人々に眠れる本(やさしい日本語、漫画、様々な言語の本)の寄贈を募り、紙のカタログを作成し、これを地域の外国人や企業などに配布することを計画しています。QRコードを通じて本の所在がわかるばかりではなく、職場や日本語教室、近くの拠点まで本の配送を依頼できるというシステムです。
言語の学習会の定期的な実施は、外国にルーツをもつ人たちとのつながりをつくるのに大変有効な手段であることが確認できました。ほかの様々な言語でも、外国にルーツをもつ人たちに主体的または補佐的な役割を担ってもらいながら学習会を行い、複言語社会の実現に寄与したいと考えています。
支援団体との情報交換において、地域を超えた横のつながりの大切さを改めて認識しました。これを解決する糸口として、生活困窮者自立支援全国研究交流大会で初めてとなる外国人支援分科会を提案し、採択されました。引き続き、支援団体と連携を強めていきます。
台風11号の影響は大きく、本の調達が難しいと判断された場面がありました。一つの国に複数の協力者が必要であることが分かりました。
この度の選書においてはインドネシアにおいて司書の協力を得ました。海外でも多言語図書館の活動は注目されており、今後波及していくことが見込まれています。海外の多言語図書館運動を私たちの経験や人的リソースによってサポートし、同時にそれらの図書館からの支援を受けるという形を実現していきたいと考えています。
◆メッセージ
「外国にルーツがある人々がばらばらに住んでいる地方都市に多言語図書館を実現する」 - この企画は、活動を共にしてくれる仲間をみつけるまでに多くの時間を要しました。そして仲間探しをする過程で、外国人や外国にルーツがある人々のおかれた現状を知り、福祉団体へのつなぎを活動の主軸に置くようになったのが、2年前のことです。
この活動期間は、本をいかに人々に届けるか、そしてどうやって地域の外国にルーツをもつ人びとと「人間的なつながり」を作るかを学ぶ1年でした。
最も大きかったのは、「自分たちが少し変わる」ことで、状況が大きく変わるということです。
たった一言、相手の言語で「こんにちは、私の名前は〇〇です」と伝えるだけで、「私」と「彼ら」を隔てる心の障壁は消えます。
地方都市に多言語図書館をつくる「机上の計画」が、血の通った活動になるために、運営者である私たち自身がこのことに気づく必要がありました。
「誰も取り残さない」というフレーズが一般化したいまでも、外国にルーツがある人々への対応は十分なものではありません。
社会課題の解決のために赤い羽根共同募金に寄せられたみなさまからご寄附のおかげで、分散型多言語図書館をつくり、それを通じて地域の人々が交流する当初のビジョンはようやくその輪郭をもつことができました。
これから多言語図書館がさらに色鮮やかな活動を展開していけるよう、引き続き私たちの活動をご支援くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。